昔のヨーロッパを舞台にした映画やゲームを見ると、「異端」という言葉が出てくることがありますね(異端審問官・異端児・異端者狩りなど)
普段聞き慣れない言葉なので、「なんだろう?」と思ったことはありませんか?
この記事では、「異端」という言葉の宗教的な意味について解説します。
ヨーロッパの人たちの宗教についての考え方がよくわかると思いますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
「異端」とはどういう意味?

「異端」とは、ごく簡単に言うと「大多数の人が信じていることからみて、間違っている考え方」のことをいいます。
例えば、とてもえらい人が「右利きの人が正しい!左利きの人は間違っている!」と言ったとしたら、左利きの人は「異端」ということになるわけですね。
歴史的には、キリスト教のとてもえらい人が、自分たちの考え方とは異なった考え方をする人たちのことを「異端」と呼び、きびしく迫害したという経緯があります。
「異端」の反対は「正統」
「間違い」の反対は「正しい」であるように、「異端」の反対は「正統」という言葉になります。
大多数の人が同意している考えを持つ人々のことを「正統派」と呼ぶこともあります。
現在でも「正統派の美少女」とか、「正統派俳優」といったようにいうことがありますね。
「正統派」とは、大多数の人が支持する顔のかたちとか、だれから見ても実力を認められている人のことを指し、その正反対に位置するのが「異端」ということになります。
「異端」を説く人は「異端者」
正統派の人から見て、間違ったものを信じたり人々に教える人を「異端者」と呼びます。
過去のキリスト教(とはいってもごく最近までのことですが)では、ローマ教皇というとても偉い人から見て、正しいと決められた教え以外の教えを信じる人は「異端者」でした。
昔は宗教で国を支配していたため、国が正しいと認めた教えを浸透させないと国民は言うことを聞いてくれません。
異端者は教会にとってとても恐ろしい存在だったので、犯罪者のように迫害されたり、裁判にかけられたりと、ひどい扱いを受けました。
「異端」はキリスト教やユダヤ教で使われた言葉
「異端」はキリスト教やユダヤ教を国教とするヨーロッパでよく使われた言葉です。
時期としてはまだ宗教が皇帝よりも力があった頃なので、古代から近世にかけてとなります。
同じキリスト教でも色々な考え方がありましたが、当時はその中の一つだけが「正統」であり他は全て「異端」という風に扱われていました。
どうやって「正統」と「異端」を決めるの?
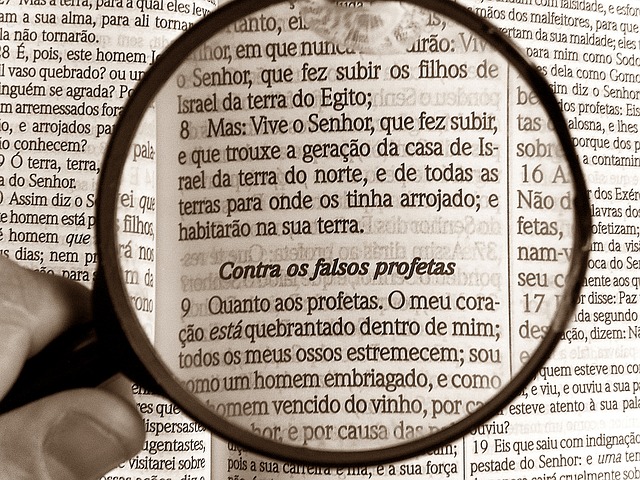
キリスト教では、教会のえらい人達が集まって話し合う「公会議」と呼ばれる集会で「正統」と「異端」を決めています。
有名なものでは、キリスト教を教えたイエス・キリストは人なのか神なのか、また別のものなのかを決める話です。
最終的に「イエスは父・子・聖霊の三位一体である」という考えが正統として扱われるようになりました。
他の考えを発表した人は異端者とされ、教会を追い出されてしまったのです。
現代でも「異端」という言葉は使われる?
現代では「変わり者」や「少数派」という意味で「異端」という言葉が使われることがあります。
必ずしも悪い意味とは限りませんが、昔の「異端」の使われ方からして良いニュアンスではありません(トラブルの元になるので使わない方が良いでしょう)
これとはまた別に「異端児」という言葉がありますが、これについては後述します。
中世ヨーロッパを舞台にしたゲームや映画では本来の意味で使われることもあります。
異端審問とは

異端審問は時期や場所によって裁判方法は様々で、大きく分けて次の3つに分類できます。
異端審問の3つの分類
- ①中世の異端審問
- ②スペインの異端審問
- ③ローマの異端審問
それぞれについてくわしく見ていきましょう。
①一般的な意味での異端審問
後で見るスペインやローマ以外の国での異端審問について見ていきましょう。
キリスト教ができて最初の時期はまだ、教会に人を罰したり裁く権利がなく、異端審問はめったに行われませんでした。
しかし、このままではいけないと思ったローマ皇帝は法律の整備を始め、最終的には異端審問は処刑までできるようになります。
というのも、当時は異端派が急増した時期が何回かあり、彼らの勢力を抑えるためにも、活発に異端審問が行う必要があったのです。
ヨーロッパの各地に異端審問所が設置されますが、イングランド(今のイギリス)やドイツではあまり定着しませんでした。
②スペインの異端審問
国として成立したばかりの頃のスペインは、キリスト教に改宗した元イスラム教徒や、元ユダヤ教徒がたくさんいた国でした。
裏返って反乱を起こすかもしれないと不安だった王様は異端審問できるようにしたがりました。
この異端審問は教会の許可を得たものではなく独自のものだったため、教皇はあまり賛成できませんでしたが王様はむりやり異端審問をできるようにします。
その結果、多くの異端者がでっち上げられたり処刑されたりし、異端審問に悪いイメージがついてしまったといわれています。
③ローマの異端審問
ローマはカトリックの総本山ですから、ローマにおかれた異端審問は、各国の異端審問に不正がないかを監督する役割を持っていました。
ローマの異端審問官は、選び抜かれた神学者や宗教の専門家だったのです。
後にローマの異端審問は「検邪聖省」という名前に変わっていて、現在もあります。
17世紀に地動説を唱えたガリレオ・ガリレイの裁判もこの検邪聖省が行っていました。
あくまで心を入れ替えさせるのが異端審問の目的
異端審問の目的は、「正統派の考えになってもらう」ことです。
異端審問といえば拷問だったり処刑だったりと恐ろしいイメージがありますし、確かに取り調べの一環として行われていました。
しかし、頻繁に死刑を言い渡して処刑していたのはスペインくらいなもので、他の異端審問で本当に処刑したことはあまりありません。
処刑は最後の手段
異端審問において、処刑は基本的に最後の手段です。
日本の裁判でも、死刑宣告は相当重い罪をおかさない限りありませんよね。
上記のように、異端審問はあくまでも「考えを改めてもらう」ことが目的なのであって、「異端者を殺すこと」ではないのです。
異端審問官とは?
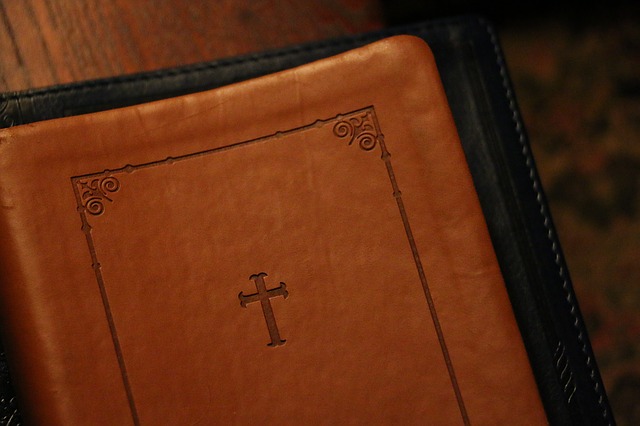
よく「異端審問官」と聞くと「異端者を捕まえて拷問したり火あぶりで処刑する人」というイメージがありますが、実際の歴史ではどうだったのでしょうか。
異端審問官とは、ごく簡単にいうと今でいう裁判官のことで、異端者や国教以外の他宗教を排除する人なのです。
異端者を裁く裁判を「異端審問」と呼び、それを行う施設を「異端審問所」と呼んでいました。
異端審問官には権力者も手を出せない
当時の異端審問官の力は絶大で、皇帝ですら彼らの邪魔をすることはできませんでした。
もし、皇帝が異端の教えを広めようとしたら、異端審問官は皇帝を裁くこともできたのです。
たとえ教会内部の人でも異端と認定されれば、相手がどんな立場であっても逮捕・裁判が可能とされていました。
宗教の力がどれほどのものだったのかを象徴する存在と言えます。
異端者狩りとは?

異端者狩りとは、簡単に説明すると、その名の通り異端者を捕まえることです。
似たようなものに魔女狩りというものもありますが、時代や目標からしてまったく違うものです。
あくまで異端の教えを信じる人を捕まえることが目的です。
狩るというと一斉摘発のようですが、実際は密告者から提供された情報を元に捜査してから逮捕するのが本来の形です。
異端児とは?
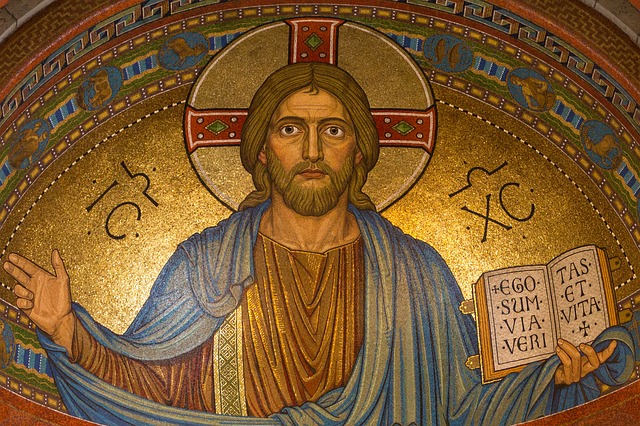
現在では「異端」という言葉そのものよりも、「異端児」という言葉の方がよく使われますね。
「業界の異端児」とか、「あの人は異端児だ」というように使われることがあります。
この異端児とは、具体的にはどういう人のことを言うのでしょうか?
「異端児」は悪い意味ではない
結論から言うと、異端児とは、「常識にとらわれず、独自の方法をとる人」のことをいいます。
つまり「人と違うことをする変わり者」という意味なのですが、必ずしも悪い意味ではありません。
皆が同じことをすることを大事とする日本では嫌われてしまう傾向もありますが、本来変わり者は悪いことではありません。
人と違うことをするのは世界を変えたり、成功する近道だったりするのです。
「児」という字があるから異端児は子供?
異端児は「児」があるからといって必ずしも子供を指す言葉ではありません。
大人に対しても使われる言葉です。
「野球界の異端児」「プロレス界の異端児」などと使われるので、どの年齢の人に対しても使っても問題ありません。
具体的にどういう人が「異端児」なの?
独自に電球などを発明したエジソンや、型破りな方法で勢力を伸ばした織田信長が異端児と呼ばれます。
現代では独特な方法でチャンピオンに上り詰めたプロレスの亀田兄弟が異端児と呼ばれることも。
世界に名前を残す天才や偉人は「異端児」と呼ばれるような変人が多いです。
ですが、それは決して悪いことではないのです。
まとめ
今回は、「異端」という言葉の意味について解説しました。
「この考えが唯一正しい」というものがある世界では、その考えに反する考え方は異端ということになります。
しかし、現代ではさまざまな考え方や宗教が認められていますから、異端という言葉自体あまり使われなくなっているのが実際のところですね。
人とはちょっと変わった考え方をする人のことを異端児と呼ぶことはありますが、むしろ「人とは違った考え方で大活躍している人」という意味で使われることが多いですね。
変わり者だからと排除したりいじめたりせず、いろんな人と仲良くできる世の中にしたいものです。